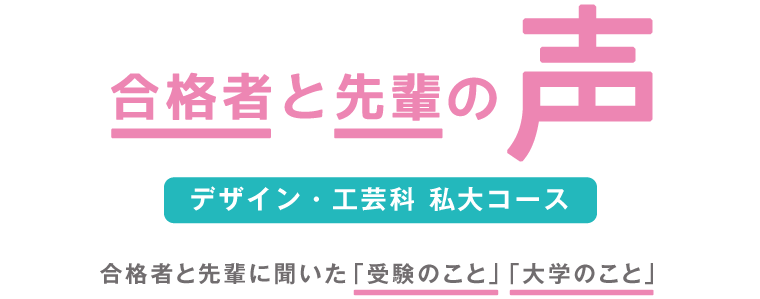
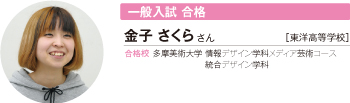
●入試が終わった率直な感想は?
1年間やってきたことを全て活かせたかというと少し悔いの残る学科もありましたが、総合的に見ると無難にこなせたかと思います。試験はあっという間に終わってしまいますが、その中でやり切れた部分が多かったのを実感しています。
●代ゼミで学んで一番印象に残っていることは?
講評のとき、上手い順に並べられないところです。個性をすごく尊重してくれるので、ネガティブな私は必要以上に自分を責めることがありませんでした。笑 あとは少人数でアットホームなんですけど厳しいときは厳しい、メリハリがあるところです。それと先生たちは面白くて、困った時に相談にもきちんと乗ってくれるところが印象に残っています。
●受験生活を送る中で、
スランプはどう乗り越えましたか?
とにかく周りの絵の上手い人達に「どう描くの?」と聞きまくりました。あとは上手い絵を見て真似したりしました。上手くいかないときは自分の中の変な固定概念に囚われているときだと思ったので、とりあえずやってみて当たりだなと思ったら取り入れる。あとは睡眠時間が削られない程度にギターを弾いたりゲームをしたりしました。
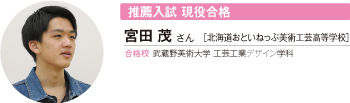
●入試が終わった率直な感想は?
やりきりました。ポートフォリオ作成、面接練習共にやりきったので、試験前に「これで落ちたら自分にとってムサビは相当レベルの高い学校だったんだと思って諦めるしかない」と思うことができました。面接の内容についても、自分の本心しか語らなかったので、つっかえることも抜けることもなく、終わった直後から自信がありました。でも、なんだかんだ合格発表まではソワソワしました。
●代ゼミで学んで一番印象に残っていることは?
琺瑯製のポットの着彩デザインが印象に残っています。それまでは形をとる段階で大分苦労していたのですが、先生のOKがでるまで何度も線の修正をしたり、明確に色分けするために明るさ毎に線で区切ったりする作業で観る目が鍛えられたと思います。3日もポットとにらめっこは辛かったし、先生のOKがいつになったら出るのか分からなかった…。
●受験生活を送る中で、
スランプはどう乗り越えましたか?
スランプとは違いますが、自分の周りの人達が遊んでいる時に、自分だけ受験勉強をしているというのは辛かったです。その頃、高校の友達はみんな遊んでいて、正直雑ざりたかったです笑。でも、ムサビを選んだのは自分がなりたいデザイナー像になるためでしたし、夢を見てメンタルを保ちました。
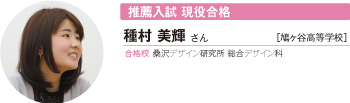
●入試が終わった率直な感想は?
入試が終わった後は、やり切った気持ちで一杯でした。これで落ちても悔いはないなと思いました。そう思えたのは、代ゼミで入試対策をしっかりやったからだと思います。入試で使うポートフォリオの作品がたまっていくにつれ、不安が自信に変わっていきました。
●代ゼミで学んで一番印象に残っていることは?
ポスター作りが一番印象に残っています。私が作った作品は野菜がテーマだったので、まず野菜の種類や売っている場所の話から始まり、テーマを色々な視点から見ることで新たな発見があったりと面白かったです。
●受験生活を送る中で、
スランプはどう乗り越えましたか?
「本当にこの道でいいのか」「自分に向いているのか」と思った時期もありました。好きなことを将来仕事にして、嫌いになったらどうしようと思いました。でも、そう思いながらも勉強していくうちに絵を描くことや、手を動かすことが好きなので、もっと勉強して嫌いになるまで!やりきるまで!つきつめよう!と思い、乗り越えました。
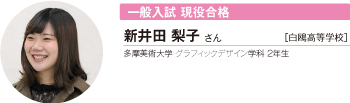
●代ゼミで学んだことで、
大学に入っても活かされていることは?
課題に対しての立案の仕方が、受験期に代ゼミで学んだことがすごく活かされていると感じます。自分の表現技法を固定せず、一つの課題に対して様々な視点から考え、沢山のエスキースを描くことで、入試だけでなく入学後の課題にもうまく応用が利くような頭の使い方を学ぶことができたと思います。入試のためだけに習得した一つの技法しかできず、入学後の課題で立案に戸惑うということが無かったのはすごく強みになりました。
●大学入学前と入学後で感じたギャップは?
中学・高校では、勉強が出来ない子は先生が手塩にかけて生徒全員を底上げしてくれるような印象がありますが、大学では課題に対応できない人はそのまま置いていかれ、きちんと付いていける人だけがぐんぐん上に登っていきます。私はその先生の対応の差にギャップを感じました。大学の先生は基本的に受け身の姿勢なので、学生側が熱心にアプローチすればするほど、自分の作品が先生の目に触れる機会が増え、力もついていくと思います。
●「学科をしっかりやっておけば良かった…」
と後悔することは?
私は自由選択の授業で中国語を取っているのですが、そちらに熱心になりすぎて、必修の英語をおざなりにしてしまったことを後悔しています。将来デザインの仕事をするにあたり語学力は必要になってくると思うので、大学受験の際に身につけた英語力は失わないように入学後も授業などを利用して、コンスタントに勉強することをおすすめします。「頭がいい」ということは確実にプラスになることなので、自分のステータスとして持っておくととても良いと思います。
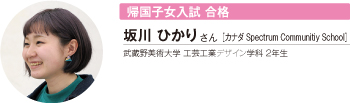
●代ゼミで学んだことで、
大学に入っても活かされていることは?
全部役に立っていると思います。デッサンも色彩構成も工業製品が多く出されるので、自分の作品のレンダリングを描く際、難なくできると思います。画面内の構図のおさめ方も、作品のプレゼンをする時、掲示するボードを作るのに活かされていると思います。あと、そこまで多くは出来なかったけど、有色下地は自分の中で一番やれて良かったと思います。大学外での黒板アートをしに行ったときやりやすかったし、レンダリングするのにも楽です。絵画の授業でも有色下地風にしたのですが、参考作品にも選んでもらえたし、自分の表現の幅も広がったと思いました。学科も、私は小論文の試験があったので、個別で課題を出してもらっていたのですが、レポート課題は前より強くなったと思います。
●大学入学前と入学後で感じたギャップは?
あまり思いつきません。私の高校も自分で履修した学科の教室に行くシステムだったし、多種多様な人も多かったので、特にギャップも感じませんでした。強いて言えば色々な分野で頭が良い人が多く思えたのですが、私が極端に勉強が嫌いなため、あまり参考にならないと思います。
●「学科をしっかりやっておけば良かった…」
と後悔することは?
社会科系は全体的にやっておけばよかったと思います。特に歴史。仏像が好きで、80分間ずっと仏像について語っている先生の授業だったり、旅先で見つけてきた文化や道具を紹介してくれる先生の授業であったり、時代背景が分かればもっと楽しめただろうなと感じました。

●代ゼミで学んだことで、
大学に入っても活かされていることは?
私は代ゼミの昼間部コースで1年間在籍していました。多摩美へ入学してから今も最も活かされているのは「臨機応変さ」であると感じています。グラフィックデザイン学科の主な実技科目に、「基礎造形Ⅰ」があります。著名な芸術家の画風や技法を参考に作品制作していく講義です。決まった工程があるわけではないので、自分自身で技法を調べて手順を設定する必要があります。そういった場面で、良い段取りを踏めたのは代ゼミで学んだ機転の大切さがあったからこそだと思います。
●大学入学前と入学後で感じたギャップは?
私は元々理系で、別の大学に通っていました。なので、前にいた大学とのギャップを今でも強く感じています。最も大きなギャップは、キャンパスはもちろん、学生や先生方の「明るさ」です。作品制作や課題などで時間に余裕がない時も詰まる時も多々あります。そんな時に、真摯に向き合って下さる先生や頑張っている友達の姿勢を見ていると負けていられないと自然と気持ちが湧いて来ます。モチベーションを高く維持できる環境にいられることに感謝しています。
●「学科をしっかりやっておけば良かった…」
と後悔することは?
小論文やプレゼンの組み立てで苦戦することがあります。多摩美の受験で小論文が出題されますが、実際の試験では小論文の出来があまり良くありませんでした。受験期間中、他の科目とバランス良くやっておけば良かったと考えています。また、私が大学1年生の際に受講していた「西洋美術史概論」と「材料学」という講義があります。歴史を追って、著名な芸術家の作品傾向や用いられる画材の変遷を見ていくという内容です。この講義をより楽しむためにも、世界史や倫理はよりしっかりおさえておきたかったと後悔しています。

